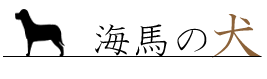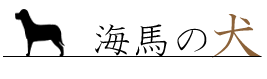屋敷は人の気配さえしない。この世から人が消え去ったのではと錯覚するほどに無音だった。
これを辛いと思うし、正直泣き出したくなるほどの孤独感があった。
それをしないのは単純に癪(しゃく)だったから。こんな理不尽なことで泣いたりしたくはなかったからだ。
強がりだと分かっていながら、一度だけ背伸びをして何でもない振りを装う。そして気付いた時には清潔になっていたシーツを巻き付け立ち上がる。
「こんなん替えるんだったら、風呂ぐれー入らせろっつの」
もう何日も風呂に入っていないのを痛感している。しかし不思議と妙な匂いがしないのは、情事の後か知らぬ間に何らかのことをあの男がしているからだろう。
だがもう二、三日は経過しただろうか。あの男を見ていない。
時間という概念が今は無いので現在が何時(いつ)なのか分からない。しかし、もう長時間見ていないので間違いなく数日は経過していると分かる。
「……………腹減ったなあ」
ぐう、と腹の虫が鳴く。
シーツをずるずると引きずりながら、扉とは真逆の何も無い壁に近寄る。真っ白で少しセメントが固められた跡が浮き上がった壁紙をそっとなぞった。
何かが記憶の淵を這うようにして瞬くようなスピードで横切る。あれはなんだと自問する前に、何故だか分からないが恐怖感が襲ってきた。
こつりとそこに額をくっ付けて逃げるように目を閉じる。
「嫌だ…独りは嫌だよ…。………海馬…っ」
崩れ落ちるようにそこに座り込んでしまったのだった。
「兄サマ…、その誓約って…」
モクバは今し方、兄から聞いた誓約の内容がどうにも信じることが出来なかった。幾ら昔の話であったとしても童話染みている。寧ろ語ることを憚(はば)られる童話の方だ。
兄が最も嫌い、現実味がないと言いそうなのにそれを弟に語った。きっと彼自身もこれを納得するまでに時間が掛かったのではないだろうか。
そんな兄よりは柔軟に出来ている自身でさえ納得出来ないでいるのに。
口の中に殆ど無い唾液を飲み込み、モクバはもう一度聞き直した。
「それって、城之内に生まれたら必然的に海馬に従うってこと?」
「…そうだ」
「でもさ…こう言ったら全部ダイナシなんだけど、城之内が従わなければいいんじゃない?反古(ほご)するってことも出来るし…」
「仮に反古する術を絶たれていたら」
「絶たれて…いたら…?…それはないんじゃないのかな…」
反古する術を絶つことは不可能だ。抜け道なんて探せば幾らでもある。
それこそ遺伝子にでも書き記されていない限りは。
「…そうだな…。無いな」
「兄サマ…?」
「無いにも関わらず、城之内は海馬に従い続けた。それが誓約だからと言ってな」
兄の話を整理するためにモクバは黙り込む。
まず兄は城之内は海馬に従う犬だと言った。犬は主と共に生き共に死ぬ一蓮托生の存在だとも言った。海馬にとって犬は一生飼い馴らすものであり、それがいない時代なんて現在を於いて存在しなかった。
つまり奇妙な誓約に基づいて海馬に忠誠を誓い城之内は従い続けてきたということだ。
では誓約はどこで交わされたのか。
それこそ気の遠くなる過去の話で、遡れば今から百年以上の昔…明治維新辺りにまで遡る。
散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。そんな言葉が散切狂言(ざんぎりきょうげん)に残されるほど、日本もだが大衆文化も一変した時代。欧米の先進技術等を取り入れるべく雇用された「御雇外国人(おやといがいこくじん)」が街中を歩くような時代だ。
その時代に於ける海馬家は西洋文化をいち早く取り入れた医者であった。御雇外国人であったドイツの軍医に直接教えを請い、あっという間にそれを取り入れ名を各方々に轟かせた。
そんな医師が城之内に出会ったのは、ある意味必然だったのかもしれない。
海馬の家の前に倒れていた少年を拾ったのがきっかけだった。名を城之内と名乗った。
城之内は明治維新直後にやってきた御雇外国人と日本人の間に産まれた子供であった。髪の色は鳶色、瞳は金色の何処からどう見ても日本人ではない容姿のせいで気味悪がられていた。幾ら日本が文明開化したとしても、全員がそれを受け入れられるほどに寛容ではない。
きっと他人には想像が付かない差別を受け少年はどうしようもなくなったのだろう。
行く宛もなくさ迷ったのか、はたまた自発的にやってきたのか。それは定かではないが海馬医師の家の前で倒れていた。
家の前で倒れられていたのでは流石に海馬も見捨てるわけにもいかず、少年を介抱することにした。
語り物にでも出てきそうな展開だぜぃ、とモクバは遥か遠い義理の先祖に向かって呟く。
「モクバ、どうかしたのか」
「ううん…ちょっと話を整理してるだけだぜぃ」
そうか、と呟き兄は深く椅子に腰掛けた。モクバが話を整理するまで待つつもりなんだろう。
この誓約が結ばれるまでの話は、ここからが本題なのである。
少年を拾った海馬医師は、まず余りにも汚れた身なりをなんとかさせるために風呂に入れた。
入り方が今ひとつ分からなかったみたいだが、それなりに自分なりに清めたみたいで見違えるほどだった。特に目を奪われたのは鳶色だと思っていた髪だ。艶やかな黄金色で金の糸といっても過言では無い美しさだったのだ。
思わず見惚れはしたが、少年が困惑した表情をしたので目を逸らす。
ちらちらと見てしまう金糸に気を取られつつ食事を与える。すると物凄い勢いで全てを平らげ、更に空になった茶碗を出しおかわりまで要求した。
海馬邸に仕えていた給仕が食糧が底を尽きたと言うまで彼は食べ続けた。途中までは遠慮を知らないと呆れていたが、度を超すとついつい感心してしまう。医師も例に漏れず、とことんまで食べ物を与えそれを眺めていた。
『貴様はよく喰うな。見ていて気分がいい』
『…?』
遠慮されたり頑なに食べないよりは、なんの躊躇もなく平らげられた方が気分がいい。しかも旨そうに食べるのだから見ていて気分が良い。
その言葉に首を傾げられたが、眩しいくらいの笑顔を少年が浮かべた。そして耳慣れない言葉を言ったのだ。
いや、医師にはとても聞き慣れた言葉。
『Danke!Sie waren für eine zarte Person gut』
(ありがとう、あんたが親切な人で良かった)
ドイツ語だ。医師の師であった御雇外国人と同じ言葉だった。
師が使用していたのである程度は理解できたが、そのネイティブなスピードでは聞き取ることが出来ないでいた。それを察したのかどうかは分からないが、ゆっくりと同じ言葉を紡ぐ。
辞書がないので流石の海馬でも全てを理解出来ないものの、大体は言っていることを理解することが出来た。尤も、少年の浮かべた笑顔を見れば礼を言っているというのは誰だって理解できることだ。
何か答えるべきかと迷い、記憶の淵にある師の言葉を思い出す。
『……Es ist keine Freundlichkeit』
(…親切などではない)
『…!Können Sie reden!Verstehen Sie meine Wörter?』
(あんた喋れるのか!オレの言ってること、分かる?)
詰め寄るように少年が海馬に近づいた。両の黄金色の瞳がくるくると動く。
期待に満ち溢れ、とても嬉しそうにしている。
『Ein kleines.Aber ich kann nicht ganz verstehen』
(多少は。だが、全てを理解している訳ではない)
『Ach so….』
(そっか…)
真実を述べたのだが、それに肩を落としてしまったので海馬はため息を吐く。
この様子では殆ど会話が成立したことがないのだろうと推測する。しかし、それがこの時代では当然だったのだ。外国語が通じる方が奇跡かつ、その少数派に出会えたことが偶然である。少年はそのことに気付いていないが。
だが先ほどの喜び様というと犬が千切れんばかりに尻尾を振っているようであった。
あの姿を見た後では、ここで無言になるのも気の毒になり仕方なしに話題を振ってやることにする。
『…Ihr Name』
(…名は)
『……Welcher Name ist es?Hier?Diese Stelle?』
(どっちの名前?ここ?あっち?)
『Es ist gut im einen, den Sie mögen』
(好む方で構わん)
『…Der Name, den ein Vater rief……jyo…ジョー…、ノウチ!』
(父さんが呼んでた名前…ジョー、ノウチ!)
それは苗字だ、と思わず日本語で突っ込みを入る海馬医師だった。
2008.03.03
ドイツ語は割と適当なので、深く突っ込みを入れられると何も答えられませんです…。